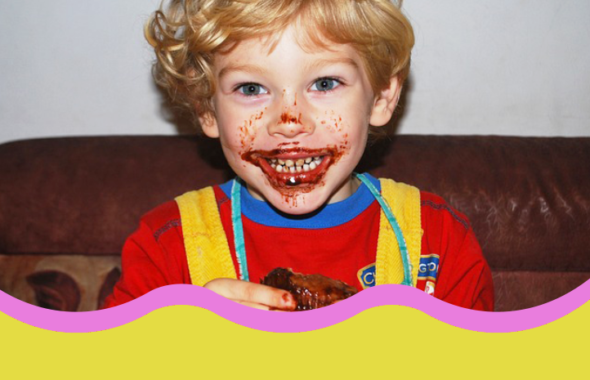子どもが開けた新たな扉から、違う人生が始まった
母になる前の私
母になる前の私は、一般的に言う高学歴。就職氷河期ではあったが一部上場企業に就職もした。男性ばかりの職場だったが、おじさま方に好かれるというよくわからない自分の特性(?)を活かし、順調にキャリアを築いた。
仕事と趣味に生き、独身貴族生活を謳歌。学生時代の友人たちが、30歳を迎えるころに続々と結婚していったが、充実した毎日を送っていたので、結婚に興味を持つタイミングが人より遅くなった。
それでも出会いに恵まれ、結婚し、高齢だったが出産した。出産が、私の人生を大きく変えた。
見ている世界が変わった瞬間
勉強自体、もともと好きな方ではあるので、色々なスキルを身に着けてきたが、母になった瞬間、それらが全く役に立たないことに気づいた。無力感にさいなまれた。
精神的に安定しているよねと言われてきたし、喜怒哀楽は男性よりは表に出てしまうものの、感情に振り回されることなど、大人になってからは皆無だったのに、我が子を目の前にして、右往左往しうろたえる自分、抑えきれない自分の激しい感情。一体これは何だろうと思った。違う自分を生きているような、こんなはずじゃないという感覚。育休復帰後、今でこそ問題発言になるが直属の上司に「時短勤務で残業できない人は、評価しないからそのつもりで」と言われたり、育児と家事のことが頭から離れず、思うように仕事ができなくなった。以前のようなパフォーマンスを出せない自分に、もどかしさを感じたし、同期が出世していくのを見て悔しかった。
それでも保育園の先生方に支えられ、保護者コミュニティにも支えられ、綱渡り状態で育児と仕事をこなした。
試行錯誤の育児。心身の健康を第一にと思いつつ、将来、自分と同じか、あるいはそれ以上の高学歴コースを歩んでほしいと、幼児教育でいかに効果を出すかを無意識に考えていた。ただ、我が子は、私の思惑通りには全く動かず。私はいらだったり焦ったり、このままではいけないという思いに駆られていた。

我が子の抵抗、“不登校”
我が子から「ママのやり方、考え方は違うんだよ」と強烈なメッセージを突き付けられたのは、小学校入学時だった。俗にいう「小1の壁」ではない。
詳細はいつか書こうと思うが、端的に言えば、我が子は不登校になった。
不登校になるなんて、夫も私にとっても青天の霹靂。何とかしなければともがいた。しかし親がもがけばもがくほど、我が子の状態は悪化した。部屋の隅に縮こまって座り、泣きじゃくる我が子を見て、はっと我に返り、激しく自分に絶望した。自分のふるまいが、我が子の心身の状態を壊していた。「パパとママも、学校も、私をコントロールしようとする!」と言われて、自分の価値観を我が子に押し付けていること、その他たくさんのことに気づいた。私は母親として、生きていてはいけないような気がした。
子どもの行動は、未来に向けての私へのメッセージだった。今だから、そう思う。
常識とか、当たり前とか、そういう判断軸は世の中にたくさんある。そして私の中にも、こうあるべき、こうすべき、という信念がたくさんあった。一方で、多様性を認め、誰も置き去りにしない社会をという考え方にものすごく賛同している自分もいる。いま、何が正しくて、何が間違っているなんて、言い切れることは少ない。変化のスピードが速く、何が起きるかわからない未来を生きていく我が子に、本当に身につけてほしい力は何だろう。自分が受けた昭和の教育と、令和の教育は何が同じで何が違うのだろうと興味を持った私は、今の小学校を知ろうと、学校のPTAの役員やボランティア活動に積極的に参加したり、オルタナティブ教育について調べたりした。
とはいえ、目の前の我が子を見ると、不安になり、将来を案じ、心配になった。勝手に苛立ち、我が子に怒りをぶつけ暴言を吐き、沢山傷つけた。望んで産んだ我が子、何よりも大切な宝物なのに、「なぜ、私を産んだの?」「みんなと違ってごめんなさい」と何度も何度も泣かれた。こんなはずじゃなかった、我が子にはだれよりも幸せな人生を送ってほしいのに、誰よりも不幸にしている母親だと、自分を責めた。私のような母のもとに生まれなければ、私がいなければ、この子はもっと幸せな笑顔に満ちていたのかもしれないと、苦しくなった。ぼーっと駅に立って、線路を見つめて吸い込まれそうになったこともあった。不定期に襲ってくるこの現象を何とか断ち切らなければと必死になり、沢山勉強したが、穏やかに過ごせる日があると、のど元過ぎれば都合よく忘れて、同じことを繰り返していた。
夫婦の信念、価値観の露呈と衝突
一番の相談相手になると思っていた夫とは、教育方針に関しては全くかみ合わず、夫婦の関係性は変わっていった。彼は、我が子の気持ちや考えに共感することはなく、不登校を単なる「わがまま」と捉えているようだった。生気が失われていく我が子を見て、心穏やかではなかったはず。それでも、社会生活を送るためには規則を守らせ、自分の考えを主張することは控え、自分の気持ちは我慢して、周りに合わせることが、我が子に一番大切なことだと言っていた。就学前にそのように教育しなかったから、不登校になったとも。だから、早寝早起きに始まり、登校しないならその代わりに1日6時間勉強しなさいとか、唯一の逃げ場所であるゲームやYoutubeの時間制限にも厳しかった。私は、我が子の好きなことを見つけることにできるだけ注力し、没頭できる時間を大切にした。先回りして援助することは止め、求められたら応じるようにし、気持ちに共感し、心配より「あなたは大丈夫」という信頼を伝えようとした。ただ夫からは、私のやり方はただの甘やかしだと言われ、私には、夫のやり方は我が子から笑顔を失うように見えた。
我が子に幸せになってほしいと思う気持ちは同じはずなのに、私達夫婦がここまでこじれたのは、予想しなかった目の前の現実への対処方法を試行錯誤する際の、情報格差なのかもしれない。自分の経験や知識に頼ることに早々に限界を感じた私は、書籍や講演等も含め外部の情報を取りに行き、第三者に相談にも行って、その中から我が子に合う方法を探した。夫にも声をかけ、相談に一緒に行ったこともあるが、処方された薬のように服用すればすぐ解決する方法を求める夫は、相談しに行っても目の前の我が子は何も変わらず、何も解決しない、非効率だと言った。夫に共有したい情報を得ても、私というフィルター越しに得た情報は公平でないと言われたこともあり、夫を相談相手と考えてはいけないと私は思うようになった。
本当は、夫にはもっとおおらかに、この子は大丈夫だから、一緒に見守っていこうと言われたかったし、もっと分かり合いたかった。
「違い」を否定するのではなく「価値」に
6歳で、多くの子どもたちと違う選択をした我が子。「違う」ということが、これほどまでに我が子を苦しめ、夫を、私を苦しめるとは思っていなかった。友達と違う選択をしていることを肯定できる瞬間と、否定したくなる瞬間。私はダメな子なんだ、と落ち込む瞬間、苦しんだからこそ自分と同じ経験をしている人の役に立ちたいと未来に前向きな瞬間。そんな浮き沈みを繰り返しながら、好きなこと、得意なことを見つけ、それに一生懸命に取り組んで、6年間を過ごした。子ども自身が、自分というものに向き合った時間だった。
例えばマーケティングの世界では、製品の差別化を図るとか、独自性を打ち出すとか、類似製品との「違い」にフォーカスし、その違いはどちらかといえば、称賛される。ではなぜ、人は「違う」と軽蔑されたり、批判されたり、あるいは自分で「違う」ことに苦しんでしまうのだろう。
私は将来、会社員という働き方ではなく、自分の力で仕事をしていこうと考えていた。だから、自分の差別化、人とは違うことでどんな価値を生み出せるか、提供できるかを考えていたはずだった。それなのに、我が子が人と違うとなった瞬間、手のひらを反すように、周りと同じであることを求めた。本当の意味で、違いを認めることとその価値を理解していなかった。私も、自分自身に向き合い続けた6年だった。
「家族」という最小の社会から、多様性を学ぶ
この6年間、自分と同じ価値観や信念で動いてもらうことを私が家族に期待してしまうこと、そうならないこと、そうならなくても良いということを学び、最も小さな社会である「家族」において多様性を認めるための体験をした。学校や、職場や、様々なコミュニティにおいて多様性を認めていくための基盤は、「家庭」から始まるのではないかと思う。夫婦関係、親子関係、きょうだい関係。一人として同じ個性を持つ人はいないはずで、「家族だから」という理由で、「同じである」ことを無意識に求める場面が多いのではないだろうか。「家族だから」という絆は大事だが、「家族だから」という鎖は不要だ。
私はまだ、母親という役割を、十分に果たせているとは言えないが、どんなことがあっても何とかなるから大丈夫と言葉や行動で示すこと、母親でもなく妻でもない私自身の人生を楽しむ姿を見せることが、娘の望むことだったことを知った。


[この記事を書いた人]いしだえいこ
なぜかおじさまに好かれる特技を持つ1973年生まれ。
長い独身貴族時代を経ての、晩婚、高齢出産後、良くも悪くも、新たな自分の一面を発見し続け、育児と仕事の傍ら、ミセスコンテストに挑戦したり、現在は推し活を楽しんだり人生を謳歌している。
仕事は傾聴をメインに、メンタリング、カウンセリング、コーチング等を組み合わせた個人セッションを提供中。