
結婚と苗字と、人生の選択肢
選択的夫婦別姓制度ができそうでできないこのヘルジャパンで、2回も結婚して離婚した私が言えることは、もういい加減になんらかの強制はなしにして、どんなことも選択肢をそれぞれ個別に持てる、決定権が自分にある制度を作って欲しいということに尽きる。
夫婦、親子は同じ姓であることが家族の結びつきだという人も多いという。いや、姓が違ったら家族の関係性や思い、絆が希薄になっちゃうのだとしたらよ?私は生まれた時の姓、つまり自分の親ととっくに違う苗字なのだから、親子の縁が希薄ってことになっちゃうの?結婚して相手の姓にした人はみなそうなの?私の長男も、結婚して妻の姓を選択したので、現在の私の姓、つまり渋谷ではない。でも息子は息子だ。今も変わらず大事な息子である。姓が違っても、仲の良い親子は仲がよく、同じ姓でも親子仲が悪い場合もある。同じ姓でも離婚するときはする。それも三組に一組も。
ちょっと複雑な話をさせてほしい。
私は生まれた時、Nという苗字だった。私の両親の姓である。20代で結婚した時にFという夫の姓を選択した。勤め人時代の私はこのFという名前で仕事をしていたわけだ。そして離婚した時には子供がすでに二人いて、彼らの姓を変えたくないという理由から、私は離婚後もFを名乗っていた。その後、30代で私は現在の渋谷という名字となる。2番目の夫の姓である。この結婚の際も、当然であるが最初の夫の姓であるFに、新しい夫を引き込むつもりもなく、名字を変えるのは当然私のほうだったということになる。こうして私は現在の名前である渋谷ゆう子となったわけだ。

さて、問題はここからである。
渋谷姓を持つ元夫と40代で離婚することとなったわけだが、離婚する際に、結婚したときに姓を選択したほうが、離婚後の姓をまた選択することができる。旧姓か、現姓かのどちらかである。しかしながら、ここが民法上の問題で、この場合の旧姓というのは、一つ前のことを指す。つまり私は、渋谷をやめようと思ったら、一番目の夫のFをまた名乗ることになってしまう。Fと離婚した際にNに戻さなかったがために、私の法律上の旧姓とやらは、この段階でFなのだ。
おかしくない?
とうに離婚した過去の元夫の姓をもう一回選択する人、、、いる?
これは民法のバグだ。明治時代だかなんだかにできた家制度の考え方のせいだ。弁護士となった息子には、「かあさんのような生き方は当時想定されてない」と一刀両断され、結果私は渋谷姓をそのまま使っている。まぁ、別れた相手のことはともかく、私はこの名前で仕事をしてきたし、本も書いているし、いわば看板のようなもので、もうこれは私の名前だ。さらに渋谷姓で生まれた3番目の子供もいるわけだし。Shibuyaって海外でも認知されやすくてなかなか良いし。そんなこんなで、制度上の問題に憤りを覚えつつ、何回も離婚した自分の生き方も人にとやかく言えるような筋合いでもなく、甘んじて法律や制度を受け入れているわけです。いまのところ。
問題といえば、この元夫はさらに今新しい家庭があって、こちらも渋谷という同じ苗字ということだ。新しい奥様やお子さんもまた、私やうちの子と同じ苗字。うちの子としては母親の違う弟と同じ苗字って、まぁまぁ変な感じもしているようではある。もちろんそれは新しいご家族のせいでもなんでもなくて、制度の問題なのだけど。(百歩譲って私のせいだけど)
さて、何回も結婚している私が言うからこそ説得力を持って言わせていただきたい。現行の制度のままなら、私がもう一回結婚した時には、絶対に相手の姓を選択する。パートナーを渋谷姓に引き込むわけにはいかない。だとすると、私は戸籍上の名前を変更するために、銀行口座やパスポートや免許証やらなんやらの面倒な変更手続きと同時に、自分の会社の登記簿も多額の事務手続きのために多額の費用を払って、法人印なども全部作り直し、戸籍上の私の名前にしなければならない。サイボウズの青野社長がこの不利益を訴えているのが本当によくわかる。とはいえ、渋谷ゆう子の名前で活動してきたこれまでの仕事との折り合いを考えると、渋谷という名前は仕事上使い続けることにはなるだろう。まさにペンネームだ。
選択的夫婦別姓を望む人が多いのは、生まれもった際の姓を個人のアイデンティティとして持ち続けたいという真っ当な思いと、姓を変更することによる社会生活上の不便さや、私のように100年前には想定してもらえなかった生き方と制度の不適合など、それはもう、人それぞれに違った理由がある。“おひとりさま”の大家上野先生だって、制度上の法律婚を結局は選んだ。法律にバグがあろうとなかろうと、現時点でそれを採用しておかなければ社会生活上不都合があるからだ。事実婚の制度もまだまだ整っているとは言い難い。一方で結婚を機に同じ姓になりたいと思う人だってもちろんいる。それもまた生き方のひとつだ。だからこそ、「選択的」になって欲しい。だれかの思いを置いてけぼりにするわけでなく、単に選ばせてほしい。そう言っているだけだ。

もうひとつ。結婚にともなう子供関係にも民法上の大きなバグがあることもお伝えしておこう。離婚した人は経験したと思うが、仮に自分が離婚の際に旧姓(私の場合はN)に戻したとしよう。離婚後の自分の新しい戸籍が勝手に作られるのに、そこに自分が育てる子供たちは自動的にくっついては来ない。子供達の戸籍を変更し、子供達の姓をNにするためには、家庭裁判所に届出て認められる必要がある。私の場合は、再婚した際に私は渋谷になったが、親権を持って育てている息子たちを渋谷戸籍に入れるため、家庭裁判所に届出る手続きをとった。渋谷姓の元夫と息子たちは養子縁組をしていないので、同じ苗字ではあるが法律上の親子関係はなく、単なる「くっついてきた妻の子供」という扱いでしかない。同じ苗字、同じ戸籍ではあっても、法律上は親子ではなく同居しているだけの家族である。家族が同じ苗字であることや、親子がみな同じ姓であることを絆だのなんだの言うなら、子供を育てる親にちゃんとセットでくっつけてほしい、自動的に!と声を大にしていいたい。そんなの一部の勝手な人だけでしょと思うなら、離婚家庭数とその子供の数をカウントしてほしい。もうこれは一部なんかじゃない。
現在の人生の選択肢の多様化に、古い法律と制度が全く噛み合わず、大多数とはいわないまでも、少なくない人たちがこのバグに付き合わされ、不利益や不満を被っている。制度はもちろん必要だし、社会が円滑に回るための規律や法的な整備はもちろんないと困る。ただ、こうした古い法律が引き起こす、現代社会とのミスマッチはどうか解消してほしいと思う。名前はその人の生き方そのものだ。100年前には存在していなかったキャリアを持った女性たち(もちろん男性も)が結婚によって不利益がでることを阻止してほしい。子供の姓をどうするかについて、柔軟な対応ができるようであってほしい。家族の心の絆と同姓かどうかは関係ないとデータからきちんと読み取ってほしい。そして何より、同じ姓になりたい人たちの思いもまた、そのままであってほしい。これから夫婦別姓が選択できるようになっていたとしても、私はプライベートの渋谷姓を放り出して、新しい姓を選ぶ。過去は過去として精算し、新しい名前で人生をパートナーと共に歩く未来を選択したい。生き方や考え方は、変化する。だからこその、法律にも制度にも変わっていくことを要求したい。時代も変わっていくのだから。
どうかどんな人も、自分の人生を「選択的」に進めますように。

[この記事を書いた人]渋谷 ゆう子
香川県出身。大妻女子大学文学部卒。株式会社ノモス代表取締役。音楽プロデューサー。文筆家。クラシック音楽を中心とした音源制作のほか、音響メーカーのコンサルティング、ラジオ出演等を行う。音楽誌オーディオ雑誌に寄稿多数。
プライベートでは離婚歴2回、父親の違う二男一女を育てる年季の入ったシングルマザー。上の二人は成人しているが、小学生の末子もいる現役子育て世代。目下の悩みは“命の母”の辞め時。更年期を生きる友人たちとワインを飲みながらの情報交換が生き甲斐である。
著書に『ウィーン・フィルの哲学〜至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』(NHK出版)、『名曲の裏側: クラシック音楽家のヤバすぎる人生 』(ポプラ新書 )がある。
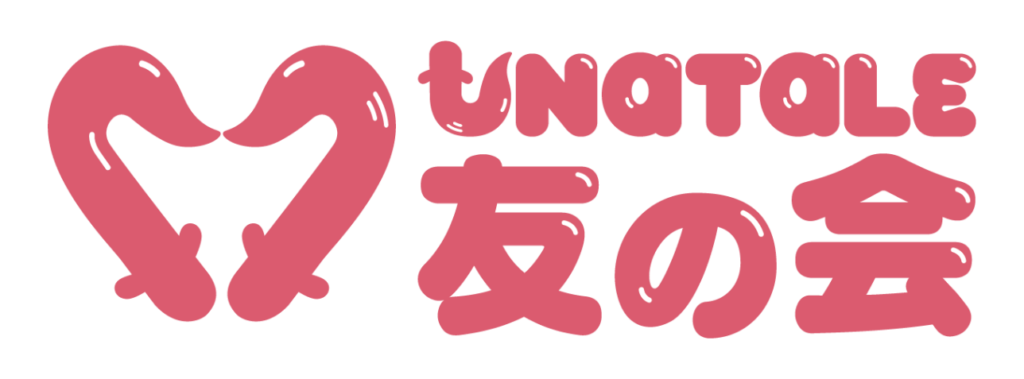
◆コラムの感想やコラムニストへのメッセージはウナタレ 「友の会」コラムニストの部屋にて。
わかる、わかる!とコラムを読んで共感したあなた、友の会でお待ちしております。
コラムニストの部屋
https://tomonokai.unatale.com/category/columnist/






